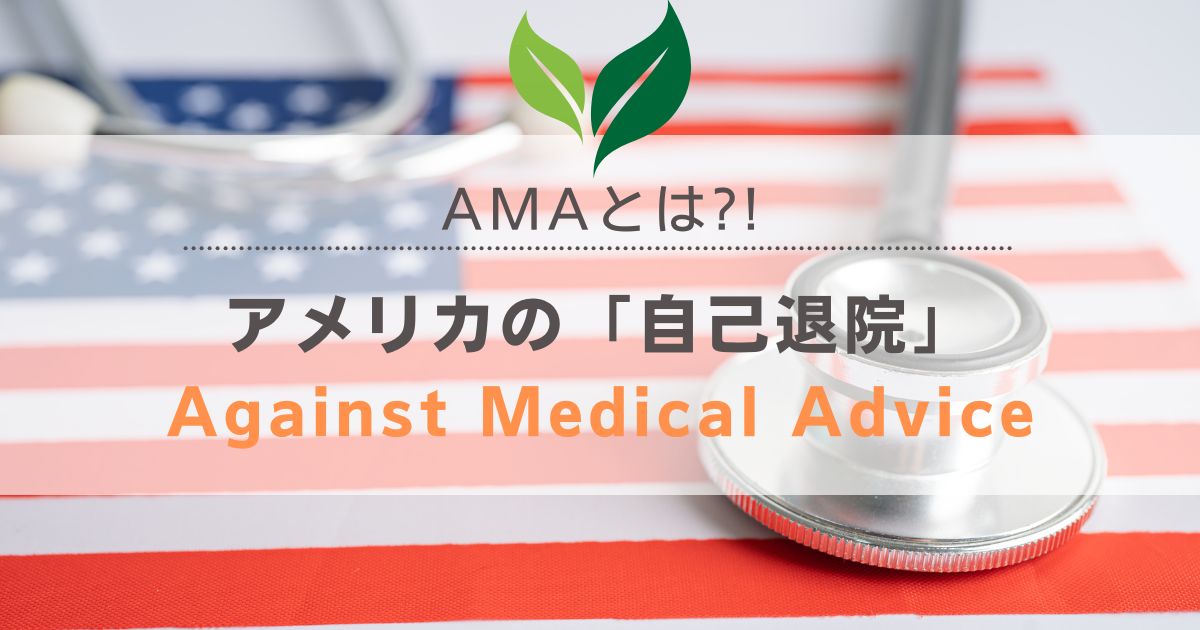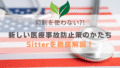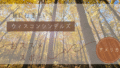こんにちは、リルです!
先日は【抑制帯・Sitter】についてお話しましたが、今日はアメリカでよく聞く「AMA(Against Medical Advice)」についてご紹介します。
AMAってなに?
AMAとは「Against Medical Advice」、つまり医療者の助言に反して患者さんが自主的に退院することを指します。
アメリカの病院ではこの“自己退院”が意外と一般的。NCLEX(看護師国家試験)でも出題されるほど、現場では当たり前に起こりうる場面なんです。
驚いたのは、AMAという言葉が高校生のCNA(看護助手)でも知っているレベルの認知度だったこと。日本でも自己退院に関する書類は各病院で用意されていると思いますが、ここまで「AMA」が一般的に使われていることに驚きました。
「え、この状態で本当に帰すの?」という現実
実は先日、私が担当していた患者さんがAMAで退院されました。
日本の感覚だと、「え?この状態で帰しちゃダメでしょ?!」と驚くような状況。それでも医師やRNが止めても、患者さんの意思があれば基本的には退院を止められません。
もちろん、例外はあります。
薬物の影響下にある場合や、意識レベルが明らかに低下している場合など、判断能力に問題があると医師が判断すればAMAは認められません。
それでも、「あなたの体だから、最終的な決定権はあなたにあります」というのが、アメリカ医療の大前提なんです。
AMA手続きの流れとCNAができる対応とは?
AMAが発生する場面は突発的なことも多く、現場はちょっとバタバタします。
以下は私が経験したケースやRNとの会話をもとにした、一般的なAMAの流れとCNAが関わる範囲のイメージです。
AMAの流れ(ざっくり)
- 患者さんが退院を希望する(医療者の判断に反して)
「もう帰る!」「ここにいたくない」といった強い意思表示がある。 - RNがまず対応し、医師に報告
患者の状態確認、意思の確認をしつつ、医師へ連絡。 - 医師が診察・説明・リスクの説明を行う
・帰宅することで起こりうる健康リスクを説明
・できるだけ説得はするが、最終的に意思を尊重 - AMAフォームのサインをもらう
・患者が自分の意思で退院することを明記
・サインがもらえないケースもある(その場合でも記録は残す) - 退院準備&記録の整理
・書類のサインが終了して初めて退院準備を行うことが出来る
※しかし多くの場合、患者はこの時点で帰る準備万端だったりする
・通常退院ではないため、通常は実施するVS測定などは実施しない。
RNにとっては「記録」が非常に重要で、何が起こったか、誰がどう関与したかを細かく記録に残す必要があります。
CNAはどこまで関わる?
CNAはAMA手続きそのものに直接関わることは基本的にありませんが、以下のような部分で間接的に関わるケースがあります:
- 安全確認(転倒リスク、移動の付き添いなど)
患者が一人で帰れる状態か?必要であれば付き添いなどをサポート。 - 患者の言動の報告
「ちょっと様子がおかしいかも?」という場合、RNに報告するのもCNAの役割。 - ナースに呼ばれるまで何もできないことも多い
AMAはかなり“判断が問われる”場面なので、CNAだけで対応することは基本NG。
私も判断が下されるまでは、必要時以外は入室せず、RNの指示を待つようにしています。 - RNへのサポート姿勢
「〇〇号室、どうなりそう?何かできることあったら教えてね」といった声かけが、チームとしての連携に大事だと感じています😊
AMAの場面ではRNの業務が非常に多く、心理的にもピリピリしていることがあるので、CNAは「見守りつつ、必要なときに動く」姿勢が大切だと実感しました。
アメリカ医療の「自由」と「責任」
アメリカでは、患者の権利や尊厳を守ることがとても重視されています。
言い換えれば、“患者さんは自分の身体のことは自分で責任を持ち、自分の意思で行動できる権利がある”という考えがベースにあるんですね。
だからこそ、AMAでの退院や、治療拒否も一種の“自由”として認められているのですが…
現場ではその“自由”とどう向き合うかが、RNとって大きな課題でもあるようです。
RNとの会話で感じた「理想と現実」
仲の良いRNと抑制帯やAMAの話をしていたときのこと。
彼女はこう話していました。
「アメリカは自由が効きすぎる。極端に言えば“拘束”できるのは刑務所だけ。それが良い面もあれば、現場の負担になることもある」
確かに日本出身の私から見ると、患者を縛らないアメリカの医療現場は理想に思えます。
でも彼女は、「毎日いろんな患者さんを相手にしていると、相手をリスペクトしない未熟な大人も多くて、本当に難しい。責任感がない人も多く、AMAで退院しても10分後に帰ってくる人もいる。」と、自由の国にいるからこその悩みを打ち明けてくれました。
患者の自由が保障されているアメリカの医療現場。
それは素晴らしいことである一方で、現場で働くスタッフの負担やジレンマも少なくないと感じた1日でした。
おわりに:医療の多様性に触れて
患者の自由が保障されるアメリカの医療。
それは素晴らしいことでもあり、同時にスタッフへの負担やジレンマも生まれます。
今回の経験を通して、医療の「自由」と「現実」をよりリアルに感じました。
日本とは違うこのシステムを知ることで、改めて医療の多様性と難しさに気づかされますね。
この記事が、アメリカの医療現場を知るきっかけになれば嬉しいです!
ブログでは他にもCNAの仕事や現場のエピソードを発信しているので、ぜひのぞいてみてくださいね👇