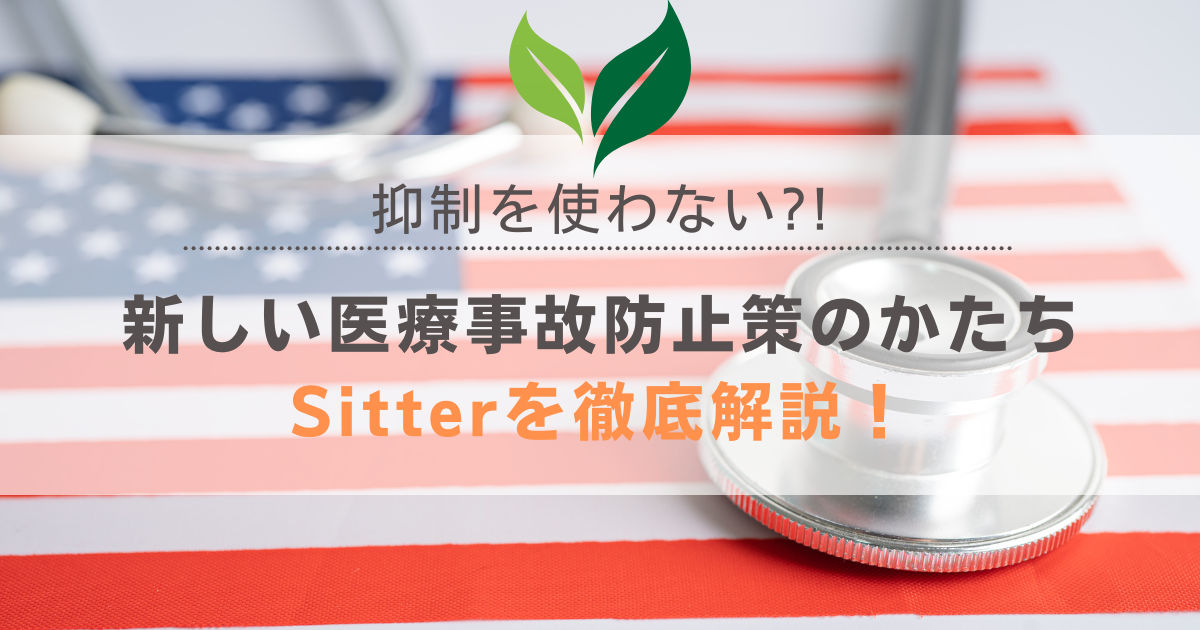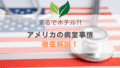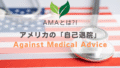こんにちは、リルです!
今日は、アメリカの病院で働いていてよく目にする「Sitter制度」について紹介したいと思います。日本ではまだあまり知られていない制度ですが、個人的にはかなり画期的で、「あーこれ日本にももっと広がったらいいのにな」と思う場面が多く感心したので、シェアさせてください😊
日本ではまだ多い「抑制帯」の現実
私が日本で看護師として働いていた頃、毎日のように目にしていたのが「抑制帯」です。
不穏な高齢者の方、点滴やチューブ類(胃管や膀胱留置カテーテル、挿管チューブなど)を自己抜去してしまう危険のある方、ベッドからの転倒リスクが高い方には、ミトン型の抑制具や胴抑制が日常的に使われていました。
特に、気管内挿管中や胃管・尿管使用中の患者さんには、“念のため”という理由でルーチンのように抑制がかけられることも少なくなく、それが原因で:
…という悪循環も起きやすかったように思います。
さらに、以前勤めていた病院では、自殺企図やOD(薬物の過量摂取)で入院した患者さんには、ほぼ100%抑制帯(しかも胴抑制・ミトン・手抑制のトリプルパンチ…)が使われていたのも印象的でした。「安全を守るため」の処置である一方で、患者さんの尊厳や自由がかなり制限されてしまうことも事実です。
抑制=診療報酬減点の対象に
最近では、2024年度の診療報酬改定で「身体拘束の最小化」が強く打ち出され、2025年6月からは入院基本料の1日40点減算が始まる予定です。
そのため、「抑制帯を使うかどうか」の判断は、ますますシビアになっていくと思われます。
アメリカのSitter制度:抑制ではなく、“見守る”という選択肢
アメリカの病院では、こういった場面で「Sitter(シッター)」という制度が活躍します。
Sitterとは、1人の患者さんに対して1人のスタッフが付き添い、病室内で常に見守る役割のこと。
「1:1 Sitter」と呼ばれることもあり、危険な行動を取る可能性のある患者さん(例:自殺リスク、せん妄、チューブ自己抜去のリスクなど)に対して、抑制帯を使用せずに、医療事故を予防する体制を整えるための制度です。
Sitterが担う役割
Sitterは患者さんに寄り添って“何もしない”ようでいて、常に見ている存在です。
その場に「いること」自体が抑制の代わりになっており、強制的な拘束や抑制具を使う必要がほとんどありません。(抑制帯の知識や使用はアメリカ社会で存在しますが、1年半の病院勤務で一度も見たことがありません)
私の働く病院では、自殺企図がある患者さんには100% Sitterが付きます。
また、認知症のある高齢者で転倒歴がある方、せん妄リスクの高い方にも、医師やRNの判断でSitterが配置されることがあります。
高齢者も活躍!Sitterの働き方と雇用形
Sitterとして働いている人たちは本当にさまざまで、高齢の方も多く活躍しています。
医療的な資格は必須ではないため、“穏やかに人と向き合う”ことができる人材が重宝されている印象です。
時給は州によりますが、ウィスコンシン州ではおおよそ$18〜20ドル前後。
オンコール制度を導入している病院も多く、必要と判断されるとすぐにSitterを呼ぶことが可能です。
CNAが臨時でSitter業務を担当することもあり、私も何度か経験したことがあります😊
New! VMT (Video Monitoring Technology)という選択肢も
最近では、VMT(ビデオモニタリングテクノロジー)を導入する病院も増えています。
VMTとは?
- カメラを使って複数の患者さんを一括でモニタリング
- 専任のスタッフがモニタールームで観察し、異変時には即座に病棟へ通報
- プライバシーを尊重し、音声のみ or 画質制限モードで使用するケースもあり
この技術をうまく活用することで、“1:1のSitter配置が難しい場合でも安全を守れる”という新たな選択肢が生まれています。
私の働く病院では、「ちょっとこの患者さん、医療事故のリスクがあるかも?」という時にもVMTが活用されており、現場では「心強い味方」として認識されています。
ちなみに、医療事故を防ぐ予防策として、
離床センサー ⇒ VMT ⇒ Sitter という順で導入されることが多いです。
Sitter制度+VMTのメリットまとめ
| メリット | 内容 |
|---|---|
| ❌ 抑制なしでも安全を守れる | ミトンや胴抑制を使わず、声かけと介入で予防 |
| 🧠 精神的不穏の悪化を防ぐ | 見守るだけで安心感を与える存在に。話し相手にも◎ |
| 🏃♀️ ADLを保ちやすい | 必要以上の床上安静が避けられ、早期回復にもつながる |
| 👁🗨 医療事故を未然に防ぐ | 転倒、自己抜去、自傷行為などのハイリスク行動に即対応 |
| 🙆♀️ 患者の尊厳を守れる | “縛る”ではなく、“寄り添って見守る”というアプローチ |
| 🎥 VMTの使用でコスト削減にも | スタッフやSitterが足りない時の補完的役割に◎ |
おわりに
「1:1で見守るなんて現実的じゃない」と思うかもしれません。
でも、アメリカの現場で大切にされている「患者の自由や尊厳を最優先に考える」という姿勢は、本来のヒューマンニーズに応える、非常に意義のある取り組みだと私は思います。
Sitter制度やVMTがすべてを解決するわけではありません。ですが、「抑制しかない」という思考から少しだけ視野を広げるきっかけには、きっとなるはずです😊
この記事が、アメリカの医療現場を知るきっかけになれば嬉しいです!
ブログでは他にもCNAの仕事や現場のエピソードを発信しているので、ぜひのぞいてみてくださいね👇