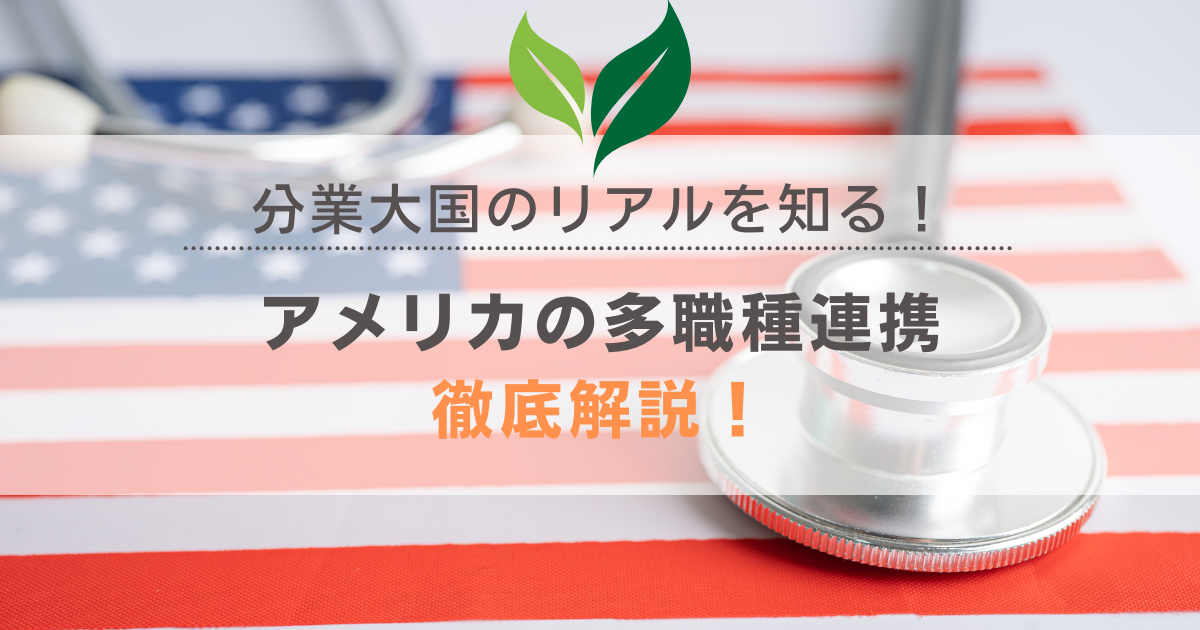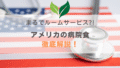分業で有名なアメリカですが、実際はどれほど分業が進んでいるのでしょうか。
アメリカCNA目線で、病院ではどんな職種がいるのかお伝えしていきます!
- アメリカの病院にいる職種13選
- 1. 医師-Physician
- 2. 看護師-Registered Nurse
- 3. 診療看護師-NP
- 4. SWATナース-SWAT RN
- 5. バーチャルナース-Virtual Nurse
- 6. 薬剤師-Pharmacist
- 7. 理学療法士-Physical Therapist
- 8. 作業療法士-Occupational Therapist
- 9. 呼吸療法士-Respiratory Therapist
- 10. 検査出しなどの患者移送-Transporter
- 11. 患者さんの見守り-1:1 Sitter
- 12. 栄養科関連スタッフ-Nutrition Services
- 13. 掃除担当者-Environmental Services (EVS)
- おわりに
アメリカの病院にいる職種13選
1. 医師-Physician
CNAは直接医師と関わることはありませんが、日本の医師と大きく役割は変わらない印象です。治療・手術を行うのはもちろん、食事制限や安静制限など患者さんの様々なオーダーも医師から出されます。
異なる点といえば、日本の某ドラマのように院長回診のようなものはなく、ナースステーションでパソコンをカタカタする姿もまず見ません。医師を見かけるのは病室内で患者さんと話している時のみです。
医師と看護師の連絡ツールは基本チャットであり、更にコードブルーではない急変時はSWAT看護師(Specialized Workforce for Acute Transport)を呼ぶことが多く、日本の医師ほど業務量が多くない印象です。
2. 看護師-Registered Nurse
看護師は医師の指示に従い医療行為を行います。投薬や傷の処置、患者指導、看護記録が業務の大部分を占めます。最も重要な役割がアセスメントと看護記録であり、多くのRNが50%以上の時間をパソコン前で過ごしています。中にはほぼずっとナースステーションにいる看護師もいるくらいです。
アセスメントとは、医師の記録や採血データ、心電図波形、レントゲンやCT画像、更に患者さんの身体/精神症状・バイタルなど様々な情報を集約し、患者さんに何が起きているか、その症状は何故起きているのか、どんな症状が起こり得るかを分析し、治療に繋げます。例えば、血圧が下がってしまった患者さんがいた場合、何故血圧が下がってしまったのか、今後どんなことが起こり得るかを分析し、初期対応や医師への報告を行います。
看護師はこのアセスメント業務が1番重要であり、訴訟大国アメリカでは、そのアセスメントと自分が何を行ったか看護記録をしっかりと書かなくてはいけません。
日本と似ている点
国は違えど、似ている部分もあります。
師長や係長などの役割はアメリカにもある
アメリカの病棟にも師長・係長(副師長)・リーダー看護師はいます。師長はUnit Lederと肩書を持っており、オフィスで事務作業や会議への出席、そのユニットへの就職希望者がいる場合は面接を行います。日本のようにスタッフの勤務表は作成しません。マネージメントを業務の大部分を占めますが、師長が希望すればRNの普段の業務も行えるようです。他の同僚と同様に患者を受け持ち、臨床で働いている師長を何度か見かけました😂
係長は教育担当、退院支援担当と日本のように担当別で数名在籍しています。係長もオフィスを持っており、基本事務仕事をしています。係長も師長のように基本事務仕事であり、臨床現場では限られた程度しか働きません。
リーダー看護師は日本のリーダー看護師のように、そのシフトの臨床におけるマネジメントを実施します。ベッドコントロールやスタッフの調整まで実施し、報連相の司令塔の立場にいます。受け持ち看護師はリーダーナースに適宜報告し、困ったことなどを相談しています。
リーダー看護師になれる看護師は限られており、その中で経験値や責任感のある特定の看護師がスタッフの勤務表を作成する役割を持っています。
患者情報メモを作成し、アセスメントを行う点は日本と同じ
看護師経験のある方はイメージが付きやすいと思いますが、日本の看護師はほとんどが当日に受け持つ患者の情報収集を行いつつ、要点や薬剤、スケジュールを書き込んだワークシートを作成します。そのシートを元に患者さんのケアやアセスメントを行い、申し送りに活用するためです。アメリカの看護師も同様に情報収集をしながらメモを作成します。異なる点といえば、日本のワークシートは患者のスケジュールベースに書く方が多いように思いますが、アメリカではバイタルや採血データなどのメモが主です。
日本の看護師は業務内容が多く、多重課題に優先度をつけて捌いていく必要があるためタイムスケジュールを立てることに重きを置いています。しかしアメリカ看護師は日本ほど業務内容が多くないため、タイムスケジュールを立てるまでもない印象です。そのため、採血データやバイタルがどう変化しているのか、どのような薬剤を使用しているか、既往歴はどんなものがあるかなどアセスメントに役立てられるメモを作成しています。
日本の看護師と異なる点
アメリカのRNを間近で見ていると、日本との違いを思い知らされます。
- 定時前出勤や残業がほぼない
- フロートRNs/CNAsが働いていたり、スタッフの入れ替わりが激しいせいか、新任/退任の挨拶が皆無(日本では朝の申し送りの時に新参者は必ず挨拶する文化があります)
- 薬剤のミキシングをほぼ行わない
- 清拭ケアやバイタル測定、血糖測定はCNAに依頼できるため自分で実施しない
- 胸腔ドレーンなど重要なデバイスが入っていない患者さんであれば、看護師は患者移送や検査出しは基本実施しない
- 輸血の認証・Wチェック・投与は看護師の業務だが、取りに行くのは看護師でなくて良い
- 配膳はデリバリースタッフが、食事介助や口腔ケア・下膳はCNAが実施してくれるため看護師は実施しなくて良い
- 退院指導は実施する必要があるが、着替えや荷物整理などはCNAが実施してくれるため看護師は実施しなくて良い
- 心電図モニターの監視を専門とする部署があるため、看護師が四六時中モニターを注視し続ける必要はない
- シッターという患者見守り専門スタッフがいるため、不穏の高齢者をナースステーションに連れてきて見守る必要がない
- ナースコールやセンサーマット作動時は基本CNAが対応してくれるため、看護師が出向かなくて良い
箇条書きで羅列すると「じゃあアメリカの看護師は一体何をしているのか?」と疑問に思いますよね。私も始めそう思いました。ずっとパソコン前にいるRNにびっくりしたものです。アメリカRNは主にアセスメント・薬剤投与・患者教育・看護記録に時間を使っています。療養上の世話は主にCNAが担当するため、病棟中を走り回る必要もなければ定時に終業することも出来ます。英語さえ出来ればお給料の良いアメリカRNは最高の仕事じゃないかとつくづく思います。
3. 診療看護師-NP
通常のRNでは行えない、一定レベルの治療や診察、薬剤処方が出来る看護師のことを指します。NPになるためには大学院で専門性を学ぶ必要があります。
病院にもNPはおり、医師と患者さんの治療について話し合って治療方針を決めたり、RNのアドバイザーとして働いている印象です。
4. SWATナース-SWAT RN
Specialized Workforce for Acute Transportの頭文字を取っており、日本でいう院内救急救命チームのようなものです。急性期治療に精通しており、「患者さんの状態が何かおかしい!」「呼吸状態が悪化してる!」「患者さんが気分不快を訴えた後に倒れた!」など急変発生時に連絡すると、患者さんの様子をすぐに見に来てくれ、的確な指示を出してくれます。
実際にCNAとして患者ケアを実施している時に、胸腔ドレーンが抜けかけている所を発見したり、患者さんが転倒したところに居合わせたことがあります。すぐさまRNに報告したところ、RNはSWATを呼び、患者状態を見てもらっていました。RNにとってSWATがいかに身近で頼りになる存在かが分かりますね。
5. バーチャルナース-Virtual Nurse
アメリカでは、Virtual Nurseという新しい看護形態が広がりつつあります。簡単にいうとオンライン看護師です。
具体的なVirtual Nurseの役割としては、ビデオ通話やチャット、専用アプリなどを通じて、患者さんの服用指導や病歴の確認、症状に応じたアドバイスなど、対面でのケアと同様のサービスを提供しています。
私の部署では、入院時のアナムネ聴取*、退院時の指導などを中心にバーチャルナースが実施しています。(*入院患者さんの病歴や既往歴、薬剤歴、現在の病状、生活状況などを、患者ないし家族から情報を収集すること)
Virtual Nurseを利用することで、病棟看護師の負担軽減・サポート、そして業務の効率化が期待されています。人手不足だと後回しにされがちな入院時・退院時対応のシステム化を行うことで、よりスムーズな患者ケアに繋げることが出来ます。
6. 薬剤師-Pharmacist
日本と同様、処方薬の調剤や薬物療法の管理を行います。
院内薬局・薬剤部はあるのですが、日本のような病棟担当の薬剤師は見かけません。更に院内で内服する薬剤は全て院内処方の薬剤とルール化されているため、持参薬の薬数チェックなどは一切実施しません。更に処方薬は全てautomated medication dispensing cabinetという機械から取り出すため、お薬カートなどを組む必要もありません。
7. 理学療法士-Physical Therapist
PTの主な役割は、身体的な機能や動きの改善を支援することです。怪我や病気、手術後の回復過程において、身体的なリハビリを提供します。
- 運動療法:筋力を強化したり、柔軟性を改善するためのエクササイズを指導します。
- 痛み管理:関節や筋肉の痛みを軽減するために、手技療法(マッサージやストレッチなど)や電気刺激を使うことがあります。
- 動作改善:歩行や立ち上がり、階段の上り下りなど、日常的な動作をスムーズにできるようにサポートします。
- 怪我の予防:将来的な再発を防ぐために、適切な姿勢や運動の方法を指導します。
Cardiac Unitで働いていますが、多くの患者さんがPTのケアを受けています。ADLに合わせた歩行器具や、適切なADLの判断などチェックしてくれるため、RN/CNAはPTとのコミュニケーションは頻繁に行います。
8. 作業療法士-Occupational Therapist
OTは、日常生活に必要な動作や活動を行えるように支援する役割を担っています。特に、障害や病気で日常生活に支障をきたしている人々に対して、社会復帰や自立を目指したサポートを提供します。具体的な業務は以下の通りです:
- 日常生活動作(ADL)の支援:食事、入浴、着替え、トイレの使用など、基本的な日常生活の活動をスムーズに行うための支援を行います。
- 適応技術の導入:特別な道具や技術(義手や義足、補助具)を使って、患者がより自立した生活を送れるようにサポートします。
- 認知・精神的なリハビリ:認知症や精神的な障害を持つ患者さんが、生活の質を維持できるように支援します。リラクゼーション法やストレス管理、社会的スキルの向上を目指すこともあります。
- 環境調整:家庭や職場での環境を調整し、安全で快適な生活が送れるように手助けします。例えば、バスルームを安全に使えるように補助具を設置したり、家具の配置を変更することもあります。
OTは整容やシャワーなどを実施してくれることもあるので、CNAにとってはとても頼りになる存在です!自宅の環境調整などの提案・相談なども活発に行われている印象です。
9. 呼吸療法士-Respiratory Therapist
Respiratory Therapistは、さまざまな疾患に関連した呼吸器系の問題を持つ患者の治療、管理、リハビリを担当しています。病棟でも毎日見かけます。
主な業務としては、患者の呼吸評価や酸素療法・呼吸サポート、人工呼吸器の管理、気道管理、吸入療法、呼吸リハビリテーションなどを行います。
日本では人工呼吸器の管理などは全て看護師の仕事ですが、アメリカでは呼吸療法士が設定の変更から人工呼吸器の立ち上げ、マスクのフィッティングなど全て担当しています。
個人的に驚いたことが、人工呼吸器で使用する加湿用蒸留水の交換さえも呼吸療法士に電話してやってもらっていたことです。その時は、正直RNが自分でしゃしゃっと変えてしまった方が早いのでは…!と思わずにはいられませんでした😂
10. 検査出しなどの患者移送-Transporter
検査出しや退院時のエントランスまでのお見送りなど、これらの移送に専門のスタッフがいます。胸腔ドレーンなどの特別なものが入っていない限り、Transporterが患者さんをストレッチャーや車いすで目的地まで連れて行ってくれます。
しかも日本ではストレッチャー移送の場合、2名での搬送がメジャーだと思いますが、アメリカでは1名が実施します。ベッドでの移送の場合でも1名です。(その代わり、ベッドには電動自転車のようなアクセル機能が付いており、強い力がなくても動かせるようになっています)
そのため日本での看護師時代は院内マップを嫌でも覚えましたが、今は基本病棟から離れることはほとんどないので、薬局や放射線科などへの道のりは未だに知りません。
11. 患者さんの見守り-1:1 Sitter
アメリカにも身体抑制は存在しますが、基本的に実施することは稀です。その代わり、転落リスクの高い患者さんや自殺企図で入院した患者さん、認知症症状が強くモニターや点滴などを引っ張ってしまう患者さんには、1名見守りのスタッフを付けることが出来ます。
そのため、身体抑制がなくても医療安全を考慮したケアが実施できるのです。
60~70代ほどの元気な年配の方がSitterをされていることも多いので、アメリカでは定年後のお小遣い稼ぎとして一定層に人気な部分もあるのではと思います。
12. 栄養科関連スタッフ-Nutrition Services
日本の病院食は、まるで給食のように決まったものが決まった時間に3食出ることが多いのですが、アメリカではまるでレストランのような環境が整っています。
各部屋にメニューと電話が設置されているため、キッチン営業時間内に電話をすれば、ルームサービスのようにNutrition Servicesのスタッフが部屋まで届けてくれるのです。
更に、血糖測定が必要な方は、部屋に届く前にRN/CNAにチャットアプリでテキストが送られてくるため、患者さんが血糖測定前に食事を取る心配もありません。
13. 掃除担当者-Environmental Services (EVS)
日本にも掃除担当スタッフはいますが、看護助手も掃除の一端を担っていることが多かったように思います。しかしアメリカではEVSが清掃に関して全て担っており、CNAは掃除をする必要はありません。
おわりに
いかがだったでしょうか?
日本の医療業界で働いている方には驚きの内容だったのではないでしょうか。個人的にSitter制度はPatient Centered Careに欠かせないため、是非日本にもアイディアや実践案が渡ったら嬉しいなと思います。
日本の保険制度では中々マンパワーが増やせないのが長年の課題ではありますが、医療サービス提供側・享受側が双方幸せになれるよう、上記職種の1つ2つでも、どんどん臨床で活躍できるようになれば、きっとより良い医療サービスに繋がるだろうなと思います。
次回もアメリカの病院でびっくりした内容をお届けします。どうぞ気長にお待ちください♪